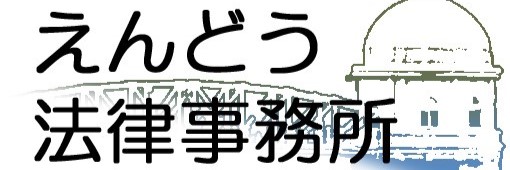「著作者は、その著作物を複製する権利を専有する」(21条)
財産権としての著作権(著作財産権)の一つに複製権があります。
なお、著作財産権とは、財産的側面から、著作物の使用権などの権利の範囲を定めたもので、著作者人格権(人格的な利益の側面から著作物に関する創作者の名誉や自由などを保護する)とは区別されます。
複製の意義と要件
「複製」の意義は、判例等を踏まえると、既存の著作物に依拠し、既存の著作物の表現上の本質的特徴(創作的表現)を直接感得できるものを再製することとされます。
つまり、依拠性及び類似性が認められることが必要です。
依拠性については、既存の著作物と同一性のある作品が作成されたとしても、例えば、偶然に既存の著作物と一致した場合などには否定されることになります。
「複製」に当たりうる行為は、具体的には、「例えば、著作物の全部または一部の印刷や、録音・録画、撮影、ダウンロードなどにより再製する行為です。
ですから、再製されたものが、デッドコピー(ほぼそのままの模倣)に至っていなくとも、複製権の侵害にあたりうる点に留意が必要です。
複製などの利用ができる場合(著作権の制限規定〔30条以下〕)
著作権は、著作権者に著作物の独占的利用権を与える非常に強力な権利です。
しかし、他人による一切の利用を許さずに、これに対する差止請求権や損害賠償請求権などが成り立つとすれば、かえって、創作活動や営業活動の萎縮を招き、文化の発展が阻害される事態が起こり得ます。このような背理を防ぐことを主眼に設けられたのが、著作権の制限規定です。
以下では、複製権等の排他的利用権が及ばないことを定めた、この権利制限規定の一部を紹介します。
私的使用のための複製(30条)
個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(私的使用)を目的とするときは、その使用する者が複製することができます。
なお、企業などの内部で使用する目的で複製をすることは、私的使用に当たらないものとされています。
ただし、次の場合(一例)は、私的利用目的であっても複製をすることはできません
①著作権を侵害する自動公衆送信(主にインターネット)を受信して行うデジタル方式の録音・録画(特定侵害録音録画〔違法ダウンロード〕)を、特定侵害録音録画と知りながら行う場合。
②著作権を侵害する自動公衆送信を受信して行うデジタル方式の複製(特定侵害複製〔違法ダウンロード〕)を、特定侵害複製と知りながら行う場合
②の場合、⑴翻訳以外の二次著作物、⑵軽微な侵害〔サムネイル画像や、著作物のごく一部など〕)、⑶権利者の利益を不当に害さないもののいずれかに該当する場合を除きます。
付随対象著作物の利用(映りこまれた著作物〔30条の2〕)
写真の撮影、録音、録画、放送など(複製伝達行為)を行うに当たって、その対象とする事物又は音に付随して対象となる 事物又は音などに係る著作物(付随対象著作物〔いわゆる映り込みなど〕)は、分離の困難性の程度などの要素に照らして正当な範囲内において、当該複製伝達行為に伴って、利用することができます。
図書館等における複製等(31条)
図書館等は、著作権法に定める場合に、図書館の図書など(図書館資料)を用いて著作物を複製することができます(31条)。詳細は、同条をご確認下さい。
事実上、図書館の複製(コピー)は利用者自身が行う場合が多いと思われますが、同条の主体は、あくまで図書館である点(利用者自身ではない)点に留意する必要があります。
引用(32条1項)
引用は、「その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるもの」である必要があります(32条1項)。
最高裁(昭和55年3月28日民集34巻3号244頁〔モンタージュ事件〕)は、「右引用にあたるというためには、引用を含む著作物の表現形式上、引用して利用する側の著作物と、引用されて利用される側の著作物とを明瞭に区別して認識することができ、かつ,右両著作物の間に前者が主、後者が従の関係があると認められる場合でなければならない」とし、明瞭区別性と、主従関係が必要であるとしました。
もっとも、その後の裁判例では、他人の著作物を利用する側の利用の目的や、その方法や態様,利用される著作物の種類や性質、当該著作物の著作権者に及ぼす影響の有無・程度などの総合考慮の上で、条文上の「公正な慣行」に合致し、また「引用の目的上正当な範囲内」であるかという問題にしたうえで、適法な引用と評価できるかを判断したものもあり、上記最高裁判例の位置づけには留意する必要があります。
現在の裁判例を踏まえた「引用」の意義などは、コチラをご覧ください。
時事の事件の報道のための利用(41条)
「写真、映画、放送その他の方法によつて時事の事件を報道する場合には、当該事件を構成し、又は当該事件の過程において見られ、若しくは聞かれる著作物は、報道の目的上正当な範囲内において、複製し、及び当該事件の報道に伴つて利用すること」ができます。
このように、事件などの報道をすることが目的である必要があります。
事務所概要
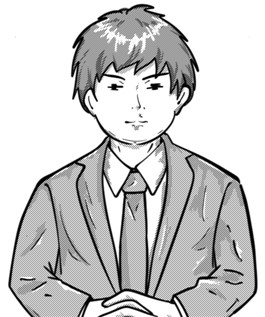
えんどう法律事務所
〒189-0014 東京都東村山市本町2-14-18-107
TEL 042-203-5842(※)
FAX 042-308-8468
メール info@endd-law.com
(平日)9:30~18:00
(土曜・休日)ご相談ください
(※)メール又はお問い合わせフォームもご利用ください