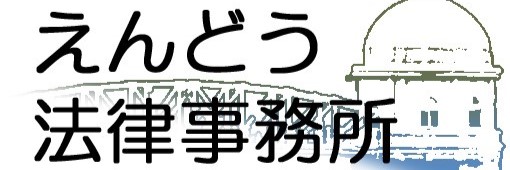著作者人格権について
著作者人格権とは、著作者の人格的利益(例えば、著作物に対するこだわりや思い)の保護の観点から、著作者の権利を定めたもので、主に、公表権や氏名表示権、同一性保持権があります。
財産権としての著作権(著作財産権)とは異なり、譲渡の対象とすることができず、実務上、「著作者人格権を行使しない」などといった著作者人格権不行使特約が定められることもあります。
また、著作者の一身に専属する権利であることから相続の対象にもなりません(59条1項)。
公表権(18条1項)
「著作者は、その著作物でまだ公表されていないものを公衆に提供し、又は提示する権利を有」します(18条1項)。
学年文集は「公表されていないもの」にあたる?
公表権の侵害の有無が争点の一つとなった事例で、中学校の学年文集に掲載された原告作成の詩について、同文集が卒業生に300部以上配布されていたことを理由の一つとして、公表されたものと認められるとし、公表権の侵害を否定しました(東京地判平成12年2月29日〔中田英寿事件〕)。
氏名表示権(19条1項)
「著作者は、その著作物の原作品に、又はその著作物の公衆への提供若しくは提示に際し、その実名若しくは変名を著作者名として表示し、又は著作者名を表示しないこととする権利を有」します(19条1項)。
その著作物を原著作物とする二次的著作物の公衆への提供又は提示に際しての原著作物の著作者名の表示に関しても同様です(2項)。
著作物の利用者が、著作者名の表示を省略できる場合として、「著作物の利用の目的及び態様に照らし著作者が創作者であることを主張する利益を害するおそれがないと認められる場合で、公正な慣行に反しない限り」であることが必要です(19条3項)。
このように、著作物の利用者が著作者名の表示を省略したことによる、氏名表示権の侵害の有無は、個々の事案により判断されることになります。
イラスト著作者の氏名を、冒頭に一括して表示した場合の侵害の有無
原告作成のイラストを掲載した書籍について、
「そこに含まれるイラストの著作者が複数いる場合,イラストごとにそれに対応する作成者の氏名を表示せず,冒頭や末尾に一括して作成者の氏名を表示することも一般的に行われていると認められることに照らせば,…,イラストごとにそれに対応する作成者の氏名が表示されていなければ氏名表示がされたことにならないとまでいうことはできず,本件書籍における氏名表示の方法が,公正な慣行に反し,控訴人の本件イラストに係る氏名表示権を侵害するものであるということはできない。」とし、氏名表示権の侵害を否定しました(知財高裁平成28年6月29日)。
学術論文著作者の氏名を、文献末尾に表示した場合の侵害の有無
一方、学術論文について、「文献末尾に,単に著作者の氏名が表示されるだけでは,文献として著作者の著作物の内容を参考としたのか,著作物を複製等するなどして利用したのかを区別することができず,著作物について著作者としての氏名を表示したものとはいえない。一般的に,論文において,慣行として,引用箇所ごとに氏名を表示するのが一般的であるのも,かかる区別を明確にするためと解される。」とし、氏名表示権の侵害を認定しました(知財高裁平成27年10月6日)。
同一性保持権(20条1項)
「著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し、その意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けないものとする」権利を有します(20条1項)。
細かい話になりますが、原著作物の全部または一部に修正増減、変更を加えて再製をした場合、その程度を大きく分けると、変更が軽微な順に、①その修正増減や変更に創作性が認められない場合、②変更などに創作性は認められるものの、原著作物の本質的特徴が失われるに至っていない場合、③変更などに創作性が認められ、原著作物の本質的特徴が失われている場合の3つに部類されます。
この場合、同一性保持権の侵害が生じ得るのは、①と②の場合です。
③に同一性保持権の問題が生じないのは、原著作物の本質的特徴が失われてしまっている以上、それは原著作物とは別個の著作物と評価せざるを得ないためです。
少しでも修正や変更を加えれば改変にあたる?
同一性保持権の侵害の有無が争点の一つとなった事例で、ウエブサイト掲載の転職情報について、ひらがなと漢字の用字上の相違や「です、ます」等の文末の表現の相違、数字上の相違があり、さらに、掲載項目の順序を入れ替えて作成されたものと認められるものの、原著作物の本質的な特徴をなす表現部分を改変したと評価できないため、同一性保持権侵害を否定しました(東京地判平成15年2月27日判時1850号123頁)。
同一性保持権の例外
「著作者の意に反する改変」に該当する場合であっても、次の場合に該当する改変については、同一性保持権の侵害にはなりません。
①教科用図書等への掲載や、学校教育番組の放送等で著作物を利用する場合において、用字又は用語の変更その他の改変で、学校教育の目的上やむを得ないと認められるもの(20条2項1号)
②「建築物の増築、改築、修繕又は模様替えによる改変」(同項2号)
③「…プログラムの著作物を当該電子計算機において実行し得るようにするため、又はプログラムの著作物を電子計算機においてより効果的に実行し得るようにするために必要な改変」(3号)
④上記①~③に掲げるもののほか、「著作物の性質並びにその利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められる改変」(4号)
やむを得ないと認められる改変とは?
東京高判平成3年12月19日(法政大学懸賞論文事件)
同一性保持権の侵害の有無が争点の一つとなった事例で、大学における学生の研究論文について、送り仮名の付し方の変更、読点の切除、中黒の読点への変更及び改行の省略は、やむを得ない改変に当たらないとしました。
一方、誤植の類に対する変更については、印刷技術の制約などから生じるような誤植で、誤植であることが明らかであって、これによって、その部分の意味内容が異なるものになるような場合でない限りは、同一性保持権を侵害する改変には当たらないとした原判決(東京地判平成2年11月16日)の判断を引用しました。
事務所概要
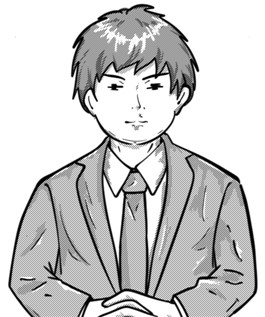
えんどう法律事務所
〒189-0014 東京都東村山市本町2-14-18-107
TEL 042-203-5842(※)
FAX 042-308-8468
メール info@endd-law.com
(平日)9:30~18:00
(土曜・休日)ご相談ください
(※)メール又はお問い合わせフォームもご利用ください