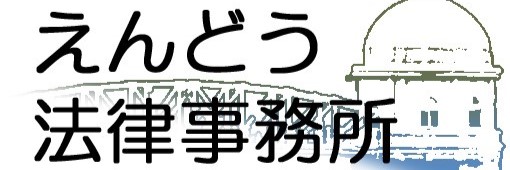「創作をした者=著作者」の例外
著作物の著作者は、著作物を現実に創作した者で(著作権法2条1項2号)、「創作者=著作者」となることは、著作権法の原則です。
では、会社で作成した著作物の著作者は、実際に創作をした従業員になるのでしょうか?
それとも、法人の名義になるのでしょうか?
このポイントを規律しているのが、著作権法(15条1項)の職務著作制度で、同条の要件を満たす場合には、実際に創作をした従業員などではなく、法人が原始的な著作者となります。
法人が著作者となる場合には、著作者に帰属する著作権や著作者人格権も、原始的に法人に帰属することになります。
職務著作が認められるためには
具体的には、次の⑴~⑸が認められる場合には、会社などの法人が著作者となります。
⑴法人等の発意に基づき
⑵その法人等の業務に従事する者が
⑶職務上作成する著作物で、
⑷その法人等が自己の著作の名義の下に公表するもの
⑸その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがないこと
⑴法人等の発意
発意とは、創作についての意思決定が、直接又は間接的に法人等の判断で行われていることを意味するとされています。
裁判例では、著作物の製作が原告会社の判断で行われたのであれば「発意に基づく」に該当するとされ、制作を発案した者が誰であるかによって判断されるものではないとしています(大阪地判平成24年2月16日判時2162号124頁〔漢字検定対策用問題集事件〕)。
なお、「法人等」には、法人のほか、法人格を有さない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものや、国・地方公共団体も含まれます。
⑵その法人等の業務に従事する者
「法人等の業務に従事する者」とは、裁判例によれば、社員などの雇用関係までは必要なく、フリーランサーであっても、法人等の指揮監督に服していればよいとされています(東京地判平成7年12月18日判時1567号126頁〔ラストメッセージin最終号事件〕)。
⑶職務上作成されたもの
裁判例では、「業務に従事する者に直接命令されたもののほかに,業務に従事する者の職務上」、「作成することが予定又は予期される行為も含まれるものと解すべき」とされています(知財高判平成18年12月26日判時2019号92頁〔宇宙開発事業団プログラム事件〕)。
また、職務著作の成立を否定した裁判例(東京地判平成16年11月12日〔創英知的財産権入門事件〕)では、原稿執筆が原告特許事務所の本来的な業務内容に含まれるものではなく、また、原告が日常担当する業務に直接含まれるものではないこと、さらに、原稿執筆が勤務時間外に行うべきことが被告により指示され、実際に勤務時間外に行われていたこと、内容も被告から具体的指示がされていなかったことなどの事実を総合勘案し、「職務上作成する著作物」に該当しないとしました。
⑷使用者の名義での公表
発行者としての名義ではなく、著作者としての名義で表示がされる必要があるとされています。
⑸契約、就業規則その他別段の定めのないこと
別段の定めがあれば、職務著作のその他の要件を満たす場合であっても、従業者が、原始的に著作者となりますが、一旦著作者が個人となった場合に、契約等により著作「者」の地位が法人等に移転するものではないことには留意が必要です。最後に
事務所概要
弁護士は、皆様が安心して、著作権などの知的財産権を利用できるよう、サポート致します。
お気軽にお問い合わせください。
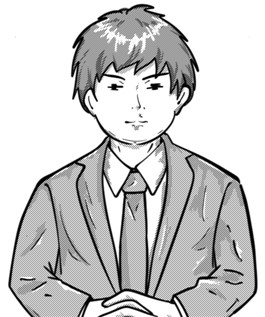
えんどう法律事務所
〒189-0014 東京都東村山市本町2-14-18-107
TEL 042-203-5842(※)
FAX 042-308-8468
メール info@endd-law.com
(平日)9:30~18:00
(土曜・休日)ご相談ください
(※)メール又はお問い合わせフォームもご利用ください