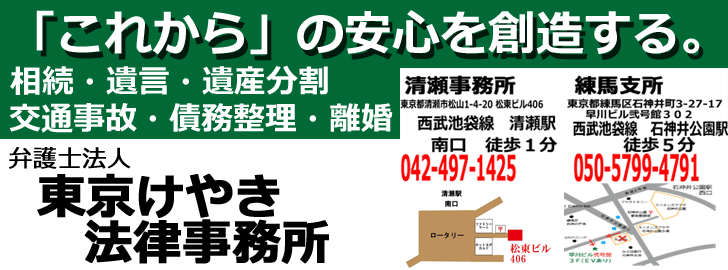はじめに
破産手続において残すことができる財産を解説します。
「個人」が裁判所に破産手続を申立て、破産手続開始決定がされると、破産した者の財産(「破産財団」といいます。)は、次の手元に残すことができる財産(「自由財産」といいます。)を除き、原則として破産管財人により換価(処分)されることになります。
以下の換価の基準は、東京地裁で運用されている基準となります。
それ以外の地裁では、若干異なる部分がありますのでご留意ください。
なお、財産を残すことができるのは「個人」のみですので、「法人」の破産手続の場合は全ての財産が換価対象となります。
99万円に満つるまでの現金
99万円を超えた部分の現金は換価の対象になります。
残高が20万円以下の預貯金
20万円を超える場合、原則、全額を残すことはできません。
残そうとする場合には、自由財産の拡張の問題となります。
自由財産の拡張とは、申立に基づく裁判所の判断により、換価の対象外となる財産(自由財産)を拡張することができる制度です。
ただし、裁判所によっては現金と預金を同視して扱っているところもありますので、ご注意ください。
見込額が20万円以下の生命保険契約解約返戻金
解約返戻金見込額が20万円を超える場合、原則、全額換価の対象となります。
ここでも、残そうとする場合には、自由財産の拡張の問題となります。
実際上の運用としては、見込額が20万円を超える場合で保険契約の継続を希望する場合には、解約返戻金相当額を破産財団に組入れる(破産管財人に支払う)ことにより、保険契約を維持することができます。
支給見込み額8分の1相当額が20万円以下である退職金債権
具体的には、支給見込み額が160万円以下の場合は、換価の対象にはなりません。
なお、退職金が中小企業退職金共済から支払われる場合などは、差押禁止債権として本来的自由財産になりますので、支給見込額に関わらず、換価の対象にはならないことになります。
支給見込額8分の1相当額が20万円を超える退職金債権の8分の7
支給見込額の8分の1相当額が20万円を超える場合、原則として、その額が換価されることになります。
実際上の運用としては、退職を強いられるわけではなく、その額を破産財団に組入れる(破産管財人に支払う)ことになります。
例えば、退職金見込額が400万円の場合、8分の1相当額である50万円を破産財団に組入れることになります。
なお、東京地裁等の運用では、破産管財人への引継予納金が自由財産から拠出される場合、当該引継予納金を破産財団に組入れる退職金見込額の一部として扱うことができます。
上記のケースを例にすると、引継予納金(20万円)を自由財産である現金から拠出する場合、退職金見込額50万円のうち20万円を破産財団に組入れられたものとして扱うことができますので、残りの30万円を組入れれば足りることになります。
処分見込額が20万円以下の自動車
東京地裁では、輸入車などの高級車を除き、普通乗用車は6年、軽自動車・商用車は4年の減価償却期間が経過した場合には、無価値とする運用です。
ただし、上記と異なる基準を用いている地裁もありますのでご注意ください。
居住用家屋の敷金債権
居住用家屋の賃貸借契約は換価等の対象外となります。
なお、事業用賃借物件等は原則として換価をすることになります。
ここも、地裁によって若干運用が異なる場合があります。
家財道具
通常の生活に必要な家財道具は、換価の対象外です。
差押えを禁止されている動産又は債権
民事執行法上の差押え禁止動産
例えば、生活に欠くことができない衣類等の日用品や食料、燃料などがあります。
民事執行法上の差押禁止債権
例えば、養育費等の扶養料債権の2分の1などがあります。
特別法上の差押禁止債権
例えば、年金受給権、小規模企業共済、中小企業退職金共済、建設業退職金共済に関する債権があるほか、傷病手当金等の保険給付受給権、生活保護受給権などがこれに該当します。
これらは一例にすぎませんので、詳細は弁護士にご相談ください。
以上に該当しない財産はどうなる?
以上に該当しない財産、例えば、不動産や売掛金、貸付金、手形金債権、有価証券類などは原則として換価することになります。
ただし、(社内)積立金や出資金、従業員持株会に関する債権など、上記記載の残せる財産(自由財産)との類似性が認められる場合などには換価を要しないとされることもあります。
これらは法律的な判断が必要とされますので、弁護士にご相談下さい。
最後に
以上は、東京地裁での一般的な換価基準となります。
債務整理に当たっては、このような財産換価の見込みを詳細に検討したうえで、どの方法がご依頼者様にとって最適であるかを判断する必要があります。
弁護士は、ご依頼者様のご事情やご希望をできる限り尊重し、問題解決のサポートを致します。お悩みの際は、ぜひご相談ください。