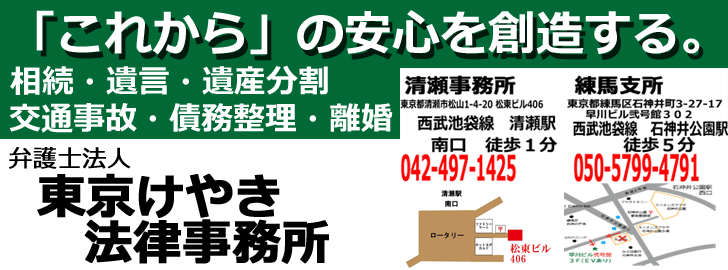個人再生には、小規模個人再生手続(一般的に、最も弁済額が減免されます)と、給与所得者等再生手続(債権者の同意・不同意に関わらず認可決定がされますが、一般的に、弁済額が高額になります)があります。
ここでは、小規模個人再生手続の流れ(東京地裁本庁申立の場合)を解説しています。
いずれの手続でも、住宅資金特別条項(住宅ローン特別条項)を再生計画案に定めることで、住宅(土地・建物)を所有しつつ、その他の債務を減免することができます(この場合、住宅ローンは通常通り支払い続ける必要があります)。
また、保有している財産の価値によっては弁済額が高額となる場合があります。
典型的な例としては、「⑼再生計画案の認可決定」の時点で、住宅(土地・建物)の価値が住宅ローン残債務額を上回る場合(アンダーローン)があります。
このような場合、財産の価値の程度によっては、早期の申立てや、他の手段を検討する必要があります。
大まかな弁済額の見通しはコチラとなります。
もっとも、法律的な判断が必要となりますので、詳細な見通しは弁護士にご相談下さい。
赤マーカー部分は、特に、ご依頼者様の協力が必須となる部分です。
⑴事務所でのご相談・面談
↓
⑵委任契約の締結
↓
⑶全ての債権者へ受任通知を送付(ここで、貸金業者等による直接取立が禁止されます)
↓
⑷申立必要書類の収集や、弁護士による債権の調査及び債権者対応、弁護士費用の分割払
↓(⑴ご相談~⑸申立まで、最短で2,3か月)
⑸裁判所に個人再生手続申立
↓(⑸から⑽再生手続の終結まで〈約6か月〉、裁判所に対し、毎月、弁済予定額を予納します〈履行テスト〉)
↓ ※予納金は再生委員への報酬(15万円)に充当され、再生手続の終結後、残額が裁判所から返金されます
⑹個人再生委員の決定・個人再生委員面接への出頭
↓(⑹から⑻意見聴取まで、裁判所による弁済計画の履行可能性等の調査が開始)
⑺個人再生手続開始決定
↓(裁判所による、弁済する債権等の調査及び確定)
↓(債権の調査結果を反映させた、再生計画案〈正確な弁済額・弁済計画の案〉の確定)
⑻再生計画案の決議(債権者に対する意見聴取)
↓
⑼再生計画案の認可決定・確定(一定数以上の債権者の不同意がない場合)
↓
⑽裁判所による再生手続の終結(ここから、再生計画案に基づく弁済(3年~5年)が開始)
↓
⑾委任契約の終了